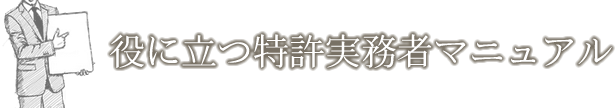こんにちは。田村良介です。
先日、ある方に教えていただきました。
ダイエットをするとき、
食べる物のカロリーの値を気にするのではなく、
それを食べることが健康につながるかどうかを気にするとよい、
ということです。
ファミリーレストランなどでは、
メニューにカロリーが表示されています。
カロリーの数字を見ると、
食べようと思ってたものも、食べられなくなります。
そういったことを続けてると、ストレスになりそうですし、
ダイエットも長続きしないかもしれませんね。
健康的な食生活を意識すれば、自然にカロリーの
高そうなものを食べることも少なくなり、
ダイエットになるのかも。
カロリーの高そうなコカ・コーラーを飲みながら、
ダイエットの話を書いております。。。
説得力がありませんね。
えーと、
お伝えしたかったのは、ダイエットでもなんでも、
適切な基準をもった方がよい、ということ。
特許の分野でも、そうです。
例えば、
特許出願をするか、ノウハウとして保護をするか、
を判断する際の判断基準があります。
特許出願をすれば、その内容は公開されてしまうことになります。
その一方で、審査の結果、特許査定がだされれば、
特許権が発生し、第三者がその発明を実施できなくなります。
特許出願をしない場合は、
発明の内容が公開されることはありませんが、
仮に、他社がその発明と同じ発明をして、
特許出願をしてしまうと、
自社で、その発明の実施ができなくなる可能性があります。
また、適切に管理しなければ、
社外に漏れてしまうリスクもあります。
特許出願をするか、特許出願をせずにノウハウとして保護するのか
について、判断をする必要があるのですが、
その判断について、基準を持っておいた方がよい、
ということです。
判断基準は、企業の戦略や製品の内容によって、
それぞれ異なると思うのですが、
例えば、『発明を実施していることが、外部から発見できるか?』
は、その一つの基準になるものです。
発明を実施していることが外部から発見できるということは、
自社で発明を実施していても、
他社にそのことが伝わってしまうということ。
それであれば、特許出願をしておいた方がよい、
という判断になります。
一方で、自社で発明を実施していても、
他社にそのことが伝わらないのであれば、
ノウハウとして管理しておいた方がよい、
という判断になります。
発明を実施していることが、
外部から発見できないということは、
他社が、その発明の内容を実施していた場合に、
他社製品をリバースエンジニアリングしても、
その発明を実施していることを発見できません。
それであれば、いくら特許をもっていたとしても、
権利行使は難しくなるので、
ノウハウとして管理した方がよい、
ということになります。
ここでは、
『発明を実施していることが、外部から発見できるか?』
ということをご紹介させていただきましたが、
もちろん、判断基準としては、
これ以外にも、
・他社が同じ技術を発明する可能性が高いかどうか
・自社の事業で実施するものであるか
・特許性があるか
などがあるかと思います。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆『出願をするか、ノウハウとして管理をするか』
について、基準をもって判断する。
☆『発明を実施していることが、外部から発見できるか?』
は、出願をするか、ノウハウとして管理をするかの
一つの基準となる。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
以前、ある起業家の方のご相談にのったときの話です。
その方は、ある玩具の発明をされ、
その発明品を販売する会社を設立されました。
この玩具について、特許出願をするだけでなく、
外観の形状についても、複数の意匠出願をした、
とのことでした。
ご相談は、この特許出願について、
拒絶理由がきたのだけど、どう対応すればよいのか?
というものですが、
ご相談の内容はさておき、
おそらくこれらの出願だけで100万円以上を
ご負担されていたと思われます。
この玩具、非常におもしろいものだと思うのですが、
まだ、ほとんど売り上げが立っていない状況で、
特許出願はまだしも、意匠出願は必要なかったのでは?
と正直なところ、思いました。
商品の形状のバリエーションはいくらでも
考えられるものでしたので、
いくつかの意匠出願で、
とてもカバーできるものではありませんでした。
後日、この方から、新しいアイデアがあるので、
特許出願をしたい、とのご相談を受けたのですが、
私は、この段階で特許出願は辞めた方がいい、
と回答しました。
起業をして、まだ、ほとんど売り上げがたっていない、
十分な資金があるわけでもない、
という状況で、このアイデアについて
特許出願をするのが、このご相談者のためになると、
とても思えなかったからです。
特許出願をするために数十万円を使うのなら、
そのお金を使って広告をうち、玩具を販売した方が
よっぽど、この会社の役に立ちます。
新しいアイデアについて特許出願をするのは、
玩具の販売で、収益があがったあとでもよい、
と考えたわけです。
我々は、出願のご依頼がお仕事になるわけで、
ご依頼をいただけることはありがたいことなのですが、
この判断は、間違っていなかったと、今でも思っています。
出願をしたから、
特許をとったから、
意匠登録をしたから、
売上があがるわけではありません。
このことをもっと早くにお伝えできていれば、
意匠出願もしなくてすんだかもしれません。
特許出願や意匠出願をすることは、
その商品やビジネスに対する1つの投資ではあるのですが、
状況によっては、もっと優先すべき投資があると思います。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆出願をしたから、特許をとったから、
売上げがあがるわけではない。
☆状況によっては、特許出願よりも
もっともっと優先すべき投資がある。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
『読書百遍意おのずから通ず』という諺(ことわざ)があります。
難解な文章でも繰り返し読めば、その意味が自然と分かってくる、
という意味のようです。
子供のころ、伯父から教えてもらったのですが、
今でも覚えています。
実際には100回も読む必要がなくて、
すごく読みにくい文章でも、繰り返し読むことで、
その意味が分かってくることがあります。
一度目に読んで気が付かなかったことが、
二度目、三度目だから気付く、ということもあります。
私もピーター・ドラッカーの著書を初めて読んだとき、
ほとんど、頭の中に入ってきませんでしたが、
そこを踏ん張って、繰り返し読んで、
少しずつ読めるようになってきたことがあります。
さて、この『読書百遍意おのずから通ず』ですが、
特許の仕事でも、活用できます。
明細書も読みにくいものがありますが、
同じところを何度も読むことで、
その意味がわかってきます。
明細書だけでなく、
拒絶理由通知を読むときにも活用できます。
拒絶理由通知は、短い文章でまとめられているため、
審査官からの説明が必要最小限に省略されていて、
その意味がわかりにくかったり、
審査官の意図を誤解しがちです。
審査官の説明がよくわからないとき、
拒絶理由通知への対応策に困ったとき、などに、
拒絶理由の内容を何度も繰り返して読むことで、
「あれ、これどういうことかな?」
「なぜ、わざわざ、こんなことを書いているんだろう?」
「なるほど、そういうことか!」
といったように、気付きが生れます。
こわいのは、審査官の考えていることを
理解しているつもりで、理解できていないこと。
審査官の判断をまちがって理解をしてしまうと、
意見書で主張する内容も、補正の内容も
的外れなものとなる可能性があります。
拒絶理由の内容さえ、正確に把握できれば、
あとは、その対策を考えるだけです。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆『読書百遍意おのずから通ず』は、
特許の仕事でも活用できる。
☆拒絶理由の内容を繰り返し読むことで、
審査官の主張を正確に把握できる。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
子供のころから、勉強は好きな方だったのですが、
宿題だけは、どうも気が進みませんでした。
特に、高校生の頃は、部活で精一杯で(言い訳?)、
宿題を、ほとんど提出しなかったような(汗)
当然ですが、成績はさんざんな結果に。。。
高校1年生のときに、夏休みの宿題を、
いっさい提出しなかったのですが、
国語の先生だけは、しつこかったです。
(今となっては、ありがたい話なのですが)
夏休みが終わった後、先生から
「読書感想文だけでも、提出しなさい」
とご忠告をいただきました。
その後も、
「2学期が終わるまでには、提出しなさい」
「3学期が始まるまでには、提出しなさい」
と何度も、何度も。
最後には、
「3学期が終わるまでには、提出しなさい」
と。
先生、ごめんなさい。
お恥ずかしい話ではありますが、
さすがに、私も、読書感想文だけは、
3学期の最終日(高校1年生の最終日)に提出をしました。
(もっと早くに提出しろよ、という話ではありますが)
当然、夏休みが終わった後も、次々と宿題がだされるわけですが、
先生は、3学期が終わるまで、
読書感想文の提出だけを求めてきました。
もし、途中で「読書感想文を提出しなさい」と言うのをやめて
「冬休みの宿題を提出しなさい」と言われていたら、
私の宿題は全滅していたかもしれません(笑)
ところで、話は、ガラッと変わります。
拒絶理由通知がだされた後、意見書を提出すると、
再度、拒絶理由通知がだされることがあります。
この後、さらに、意見書を提出しても、
結果として拒絶査定がだされると、
拒絶査定不服審判を請求することになります。
このように審査官と何度もやりとりをする際、
途中で、反論のポイントを変えてしまうのは、
あまり得策でない場合があります。
例えば、
「A手段と、B手段と、C手段とを備える通信装置」
という請求項について、新規性・進歩性がないとの
拒絶理由が通知されたとします。
一度目の意見書提出の際に、A手段をa手段と補正して、
「通信速度に優れる」と主張したとします。
ですが、この反論が認められず、
二度目の意見書提出の際に、C手段をc手段と補正して、
「消費電力が小さい」と主張したとします。
このような場合、
二度目の意見書提出で、特許が認められたとしても、
あまり良い対応ではないかもしれません。
というのは、
もしかすると、一度目の意見書提出の際に、
C手段をc手段と補正していれば、
A手段をa手段と補正しなくても、
特許が認められたかもしれません。
このように、審査官とのやりとりの途中で、
反論のポイントを変えてしまうと、
結果的に、
特許権の権利範囲が狭くなってしまうことがあります。
もちろん、例外はあるとは思うのですが、
2度目の補正の際に、
a手段と相乗効果を発揮して、
「通信速度に優れる」ことがさらに主張できるような、
別の補正を考える方が、
より有効な権利の獲得につながると、言えそうです。
先ほどの国語の先生のように、
同じポイントで、何度も何度も審査官の理解を得る、
ということが、より有効な特許権の取得につながります。
先生のご指導が、今の仕事にも活きています(笑)
先生、ありがとうございます!
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆審査官とのやりとりの際に、反論のポイントを
変えることは、得策ではない場合がある。
☆同じポイントで反論できないかを考えることが、
より有効な特許権の取得につながる。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
あけましておめでとうございます。
田村良介です。
本年もよろしくお願い申し上げます。
「一年の計は元旦にあり」
と言いますが、もう計画や目標を立てられましたでしょうか。
年の初めに目標を立てたとしても、
多くの場合は、すぐに、その目標を忘れてしまうそうです。
私も、思い当たります。。。
「ダイエットをする」と宣言しても、
3日後には、甘いものを食べているとか(汗)
目標を忘れないための方法としては、
目標を紙に書いて、目標を書いた紙を、持ち歩いて見ること、
だそうです。
日頃から、目標を意識することで、目標を達成する可能性も、ぐっと高まる、
ということなんだと思います。
「○○大学合格!」といったように、目標を紙に書いて、壁に貼る、
というのは、良い方法なんですね。
毎年、掛け声になっているダイエットを、
今年こそは、掛け声に終わらせないようにしたいです。
さて、今日の本題です。
特許請求の範囲は、
権利を受けようとする発明を特定する、
という役割をはたすものです。
一方、明細書は、
その発明の内容を具体的に説明する、
という役割をもっています。
言い換えれば、明細書は、
特許法36条4項1号の実施可能要件、
(当業者が発明を実施できる程度に記載されていること)
特許法36条6項1号のサポート要件、
(特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載したものであること)
を満たすための役割をはたすものです。
実は、これだけではなく、
明細書はもう一つの役割をもっています。
それは、
将来的に、
特許請求の範囲を補正する必要がでてきたときに、
その補正の根拠となる、
というものです。
明細書を書くとき、
実施可能要件とサポート要件については、意識をしながら書きますが、
補正の根拠を記載している、ということは、
意識をしないと忘れがちになります。
日本語の文章は、主語や述語が省略されていても、
前後の文脈で、なんとなく意味が通じるような文章になることがあります。
ですから、明細書を書いているときに、
曖昧な表現になっていることに気が付かない、
必要なことを省略していることに気が付かない、
といったようなことが、起こります。
その結果、いざ補正をしようとなると、
明細書をもう少し明確に書いておくべきだった、
ということになります。
対策としては、
明細書を書くときに、
将来、この記載をもとに、特許請求の範囲を補正できるか?
ということを意識すること。
これで、曖昧な表現も、かなり減らすことができます。
目標も、日頃から意識をすることで、
達成の可能性が高まるのだと思いますが、
明細書も、補正の可能性を意識することで、
曖昧な表現ではなく、より明確な文章を書くことができます。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆明細書を書くときに、『補正の根拠を記載している』
ということを意識をしないと忘れがちになる。
☆補正の可能性を意識しながら、明細書を書くことで、
明確な文章を書くことができる。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–