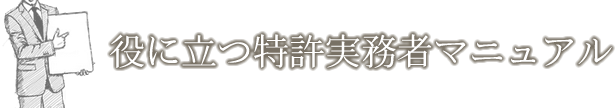こんにちは。田村良介です。
「ジョジョの奇妙な冒険」という漫画をご存知でしょうか。
1987年から連載されている、大ヒット漫画です。
30~40代の男性の方なら、
多くの方がご存知ではないかと思います。
私は中学生の頃から、大ファンでした。
最近も「ジョジョの奇妙な冒険 第4部」が
映画化されることが話題となっています。
先日、その作者である荒木飛呂彦さんの
「荒木飛呂彦の漫画術」という本を読みました。
本のコンセプトは、
荒木飛呂彦さんが、漫画の描き方の秘密を、
実際の作品を題材にして、包み隠さず説明する、
というものです。
読んでみて、すごくおもしろかったです。
「ジョジョの奇妙な冒険」が売れているのには、
やはり理由がある、というのが分かる本です。
印象に残ったのは、
ひとつのセリフ、ひとつの絵に、
意味や目的がこめられている、ということ。
「今日はパスタでも作ろうかな」というセリフで、
・主人公はイタリアンが好き
・自分で料理を作る人
・たぶん家族はいない。ひとり暮らし
・貧乏ではない
といった多くの情報を伝えることができる、
とのこと。
さすがに、荒木飛呂彦さんのように、
一つの文にたくさんの意味をもたせる、
ということは難しいですが、
日ごろ、明細書や意見書、お客さんへの提案書など、
大量の文章を書いていることもあり、
一文一文に目的を持たせることが、
読み手に伝わりやすい文章になるのではないか
ということは、感じていました。
例えば、意見書では、
「審査官殿は、拒絶理由通知書で・・・・と
述べられております。」
「しかし、引用文献1の【0001】では、
・・・・と記載されており、
本願発明の発明特定事項とは異なります」
「本願発明では、この発明特定事項を有する
ことにより、・・・という優れた効果を奏します」
「また、引用文献1は「・・・」を課題とするものです」
「引用文献1において本願発明の発明特定事項を採用すると、
「・・・」という引用文献1の課題を解決することは
難しくなります」
「よって、引用文献1において、本願発明の発明特定事項を
採用することは、当業者にとって、容易なことではありません」
といったように、文章を進めていきます。
1つ目の文で、審査官の判断の内容を説明し、
2つ目の文で、本願発明と引用文献1が異なることを説明し、
3つ目の文で、本願発明に優れた効果があることを説明し、
4つ目の文で、・・・
このように、
それぞれの文の目的・役割、伝えようとするメッセージが
明確に意図されているのが、
理想的ではないかと。
次の文章を書くために、この文章を書いている、
といったイメージでしょうか。
あたかも文と文がリレーで結ばれて、文章になっている、
そうすると、読みやすく伝わりやすい文章に
なるのではないかと思っています。
それぞれの文の目的・役割を意識せずに文章を書くと、
一つの文で、二つ以上のことを説明しようとして、
分かりにくくなったり、
同じことを繰り返し書いて、文章が冗長になったり、
といったことになります。
ここでは、意見書を例にしましたが、
もちろん、
メールなどで、相手に何かを伝える場面でも
活かすことができるかと思います。
とは言っても、
私もまだまだですので、
これからも精進して行きたいと思っています。
このメールマガジンはどうかって?
それは言わない約束です(笑)
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆一文一文に目的を持たせることが、
読み手に伝わりやすい文章になる
☆次の文章を書くために、この文章を書く
というイメージをもつ
————————————————————————
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————
こんにちは。田村良介です。
かなりのご無沙汰になるのですが、
メールマガジンの発行を再開させていただきます。
特許事務所でクライアント企業の特許出願や
特許活動等を支援する中で培った、
考え方やノウハウ、気付いたことなど、
皆さまのお役に立てそうな情報を発信していきたいと
思いますので、
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
中学生のころ、毎年、夏休みの宿題として、
読書感想文がだされていました。
これが、いやでいやで。
心の中で気になりつつも、手につかず。
気が付けば、もうすぐ夏休みも終わり。
毎年、この繰り返しでした。
大変お恥ずかしながら、
私が読書感想文の題材とした本は、
3年間、同じでした(笑)
中学二年生、三年生のときは、一年生のときに
読んだ本のことを思い出し、
本を読まずに読書感想文を書いて、提出したわけです。
国語の先生も、毎年違ったので、バレません。
読書感想文が宿題として出されるのは、
本を読むことが目的の一つだと思うのですが、
私の場合は、宿題を提出することが目的化してました。。。
この話とは、次元が違いますが、
特許の仕事をしていると、
特許をとることそのものが目的化してしまう、
そんなことがあります。
ですが、特許をとること、そのものが目的ではないはず。
企業が特許活動をすることの目的は、
他社と比べたときの事業の優位性を確保すること。
例えば、特許出願をするかどうかの判断は、
特許になりそうだから特許出願するのではなく、
特許をとることができたら、事業の優位性が
確保できるから特許出願をする、
ということだと思います。
拒絶理由通知がだされたときも、
特許をとることを目的にしているのと、
事業の優位性を確保することを目的にしているのとでは、
請求項の補正のしかたも変わってきます。
以前、こんなことがありました。
米国出願について、
オフィスアクションがだされたのですが、
非自明性(日本でいうところの進歩性)が
ないとの拒絶理由が挙げられていました。
現地代理人からの提案は、独立クレームを
下位のクレームで限定することでした。
現地代理人からの提案どおりに補正をすれば、
特許になる可能性は非常に高いと思われたのですが、
ただ、その下位のクレームは、すでに数年前に
すたれてしまった技術に関するものでした。
そのため、この下位のクレームで限定してしまうと、
仮に、特許をとったとしても、
クライアントの製品をカバーするものでもなければ、
他社の牽制にもならないと、考えられました。
私としては、現地代理人の提案どおりでは、
まずいと思いましたので、
クライアントの製品をカバーするような補正案を
提案させていただき、
最終的には、その内容で特許にすることが出来ました。
このように、
特許活動の目的を意識しながら、
一つ一つの仕事にあたっていくことで、
特許をとったけど、意味のない特許だった、
というようなことを、減らすことができます。
仕事全般に言えることですが、同じことをするのでも、
目的が変われば、やり方も変わってきます。
また、目的がぶれていると、良い仕事ができなくなったり、
その場、その場で判断が異なったり、場当たり的になります。
私自身も、目的がぶれないように、
意識をしながら、仕事に取り組んでいきたいです。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆特許活動の目的は事業の優位性を確保すること。
目的を意識することで、有効な特許活動を行うことができる。
————————————————————————
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————
こんにちは。田村です。
先日、以前から気になっていた映画を観ました。
2006年に公開された作品なのですが、
東野圭吾さん原作の「手紙」を映画化したものです。
具体的な内容は割愛させていただきますが、
ラストシーンでは、涙が止まりませんでした(笑)。
20代のころは、映画を観て泣くこともあまり
なかったのですが、30代に入ってからというもの、
涙腺が最大級に弱くなってしまったようです。。。
東野圭吾さんと言えば、言わずと知れたミステリー
の巨匠ではありますが、この作品に限って言えば、
ミステリーの要素はなく、感動できる作品だと思います。
ご興味のある方は、是非、どうぞ。
それでは、本題です。
特許請求の範囲を記載するとき、
出願しようとしている技術の中で、最も重要と
思われる発明に着目して、請求項1を記載しますが、
何を従属請求項として記載するべきか?
というご質問をいただくことがあります。
私としては、何を従属請求項として記載するかの
判断基準は2つあるのではないかと、考えています。
審査において、仮に、請求項1の新規性・進歩性が
否定されたとしても、進歩性を主張できるものであるか?
というのが1つ目の基準です。
請求項1の特許性が認められない場合でも、
従属請求項で何とか特許を受けたいわけですから、
進歩性を主張できる可能性のあるものが望ましい、
といえます。
従属請求項が、その分野において、当然に知られている
ような内容であれば、この基準を満たさない可能性は
高くなります。
もう1つは、
請求項1の代わりに、その従属請求項の内容で特許化された
場合に、特許権として取得したいものであるか?
という基準です。
いくら進歩性を有するものであっても、他社に対して牽制
とならなかったり、自社製品とはかけ離れたものであれば、
そもそも特許にする意義が薄くなりますので、このような
視点も必要であるかと思います。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
———————————————————-
こんにちは。田村です。
先日、インターネットのニュースで、
「勝率100%のじゃんけんロボット」が開発されたとの
ニュースが掲載されていました。
東京大学の情報理工学系研究科で開発されたもので、
ロボットは指で、グー、チョキ、パーをだすそうです。
なぜ、100%でじゃんけんに勝てるかというと、
ヒトの手の画像を1000分の1秒ごとに認識し、
相手が何を出すのかを、瞬時に判別しているようです。
ロボットは、グー、チョキ、パーのどれかのうち、
相手に勝てるものを選択して、ヒトが手を出した
1ミリ秒後に、手をだすそうです。
後出しだと気付かないほどの超高速で、
後出しじゃんけんをするということです。
いや~、おもしろいですね。
それでは、本題です。
特許出願の後、審査が開始されると、
特許庁から、発明に進歩性がないとして拒絶理由通知が
届くことがあります。
拒絶理由通知の内容を読んでみると、複数の引用文献を
組み合わせて進歩性がない、とのこと。
どう対応するべきか、悩むわけですが、
こんなときに、非常に便利な方法があります。
それは、発明の内容を全く知らなかったと仮定して、
拒絶理由通知で引用された文献を組み合わせて、
発明をすることができるだろうか?
と考えます。
すると、
発明の内容を全く知らない人であれば、
複数の引用文献を組み合わせても、その発明と同じような
ものを発明することは、難しいのでは?
と気づくことがあります。
審査官は、発明の内容を知っているから、簡単に、
進歩性がないと言えるわけで、
実際には、そんな簡単に発明できるものではありません。
つまり、審査官は「後出しじゃんけん」しているので、
それを見破れば、特許になる、ということです。
じゃんけんロボットの後出しを見破ることは、至難の業ですが、
審査官の後出しであれば、もう少しハードルが低くなります。
あとは、
なぜ、複数の文献を組み合わせても、その発明と同じような
ものを発明することが難しいのか、その理由を考えます。
この理由が反論の切り口になります。
是非、お試しください。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
こんにちは。田村です。
少しご無沙汰しておりました。
さて、よくあるご相談の一つとして、
特許出願前に、試作品を外部に提供したり、
製品を販売してもいいですか?
というものがあります。
ご存知のように、特許出願をする前に、
発明品を試作品として第三者に提供したり、
製品として販売すると、発明の新規性が失われます。
そのため、発明品を外部に提供する前に特許出願を
することが必要になります。
ただ、特許出願前に試作品として発明品を外部に
提供する場合でも、
試作品の提供先と秘密保持契約を結んでいれば、
新規性は失われないことになります。
簡単に言うと、
秘密保持義務を負っている第三者に対しては、
特許出願前に発明品を提供したとしても、
発明の新規性が失われることはありません。
また、仮に特許出願をするよりも前に、発明品を試作品
として第三者に提供したり、製品として販売したとしても、
「新規性喪失の例外規定の適用」の手続を行えば、
特許出願前のこれらの行為をもとに、新規性が失われる
ことはなくなります。
この非常に便利と思える「新規性喪失の例外規定の適用」
ですが、弱点としては、外国に出願をする場合です。
国によっては、このような特別な取扱いもなく、
特許出願より前に、発明品を外部に提供すると、
新規性が失われ、特許が認められなくなる場合もあります。
ですから、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合は、
将来的に外国出願をする可能性があるのか?、
どこの国へ出願するのか?
等を十分に考慮したうえで、判断する必要があります。
発明品について外部に公表する前に、余裕をもって特許出願を
しておくのが、当然のことではありますが、ベストです。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
———————————————————-