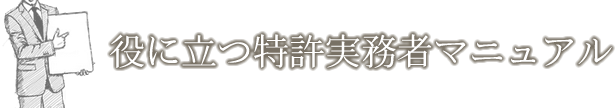こんにちは。田村です。
暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
事務所では、エアコンのお世話になっていますが、
温度を下げすぎると、体によくありません。
うちの事務所では、小型の扇風機を活用して、
空気が対流するようにしています。
そうするだけで、エアコンの温度をそれほど
下げなくても、快適な空間が作れます。
さて、本題です。
特許請求の範囲や明細書を補正するとき、
どこまでの補正が認められて、
どこまでの補正が認められないか、
迷うことはないでしょうか。
補正の認められる範囲ですが、
「出願時の明細書等に記載した事項」であれば、
補正が認められることになっています。
特許庁の審査基準によると、
「出願時の明細書等に記載した事項」とは
「出願時の明細書等に明示的に記載された事項」
だけでなく、
「出願時の明細書等の記載から自明な事項」
も含まれます。
この「自明な事項」をどう解釈するのか、
非常に難しい問題です。
特許庁の審査基準によると、
「補正された事項が、「当初明細書等の記載から自明な事項」
といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、
これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、
その意味であることが明らかであって、その事項がそこに
記載されているのと同然であると理解する事項でなければ
ならない」
とあります。
つまりは、当業者であれば、
誰が見ても明細書に記載されているも同然である、
と言えるような事項でないかぎりは、補正は認められない
ということです。
明細書に明示的に記載されていない事項で
補正したとしても、
実際には、それほど簡単には認められません。
明細書に明示的に記載されていない事項を
追加する補正が可能な場合もありますが、
できれば、
明細書に明示的に記載されている事項で
補正をする方が良いことはいうまでもありません。
明細書を作成するにあたっても、
将来的に補正をすることができるかを考慮しながら、
明細書を記載していくことが好ましい、といえます。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
こんにちは。田村です。
先日、拒絶理由通知への対応セミナーを実施しました。
足元の悪い中、6名の方にお集まりいただきました。
ありがとうございました!
数か月おきにはなりますが、今後も定期的に実施して
いきたいと思っています。
さて、本題です。
ご存知のように、特許出願をして1年6か月が経過すると、
その出願の内容は公開されます。
公開された特許情報は、特許電子図書館(IPDL)を
利用すれば無料で閲覧できるものですが、
実は、情報の宝箱ではないか、と思っています。
以前、こんなことがありました。
特許電子図書館で、とある企業の出願を調査していたところ、
どうも、その企業がまだ製品化できていない、ある装置について、
特許出願がされていました。
当時、その分野で製品化に成功している企業は、別の一社のみで、
この企業が独占状態にあったのです。
すると、その半年後、私が特許出願の調査をしていた企業が、
この装置について、製品化に成功したとのニュースリリースが
だされていました。
つまり、特許情報は、製品化されたり、ニュースリリースが
出される前に、
その企業が何を開発しているのか、
どの市場を狙っているのか、
を知ることができるツールであるわけです。
また、同じ製品であっても、特許明細書の【発明が解決しよう
とする課題】の欄は、それぞれ異なります。
この課題の欄を見ていると、
その企業が何を課題と考えているのか、
どういう特徴を有する製品をつくろうと考えているのか、
などについて、その傾向が見えてくることがあります。
先行技術の調査とは違った視点で、
特許情報を活用するのも有効です。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
こんにちは。田村です。
最近、株式会社セブン&アイ・ホールディングスの
鈴木敏文さんの「売る力」という本を読みました。
この本の中で、
売り手は「お客様のために」ではなく、
「お客様の立場で」考えなければならない、
ということが書かれています。
「お客様のために」と「お客様の立場で」は、一見、
同じようですが、実は全く違うということなのです。
「お客様のために」というのは、場合によっては、
売り手側の価値観の押しつけになるかもしれません。
「お客様の立場」にたって考えるからこそ、
お客様のニーズに沿った商品・サービスが提供できる、
ということなのだと思います。
考えたのですが、このようなことは、
他でも言えるかもしれません。
例えば、身近な人間関係の中でも、「誰かのために」と
思ってしたことが、「誰かの立場で」考えたものでなければ、
「誰か」にとっては迷惑なものでしかなかったりします。
私自身、「お客様の立場で」、「誰かの立場で」、
まだまだ考えることができていないなぁ、
と、この本を読んで、反省をさせられました。
さて、本題です。
特許庁からの拒絶理由通知に対応する際に、
私が大切だと考えていることがあります。
それは、
「特許が取れるところで権利化する」のではなく、
「特許を取りたいところで権利化する」という意識を
もつこと。
当たり前のことのようですが、我々のように、
特許事務所の代理人という立場でいると、
お客様が特許を取りたいところは何か?
という視点ではなく、
ついつい、特許を取れるところはどこか?
という視点で、対応策の提案をしてしまいがちです。
ですが、特許を取れる可能性が高い範囲で、
請求項を補正して、特許が認められたとしても、
自社製品をカバーしていなかったり、或いは、
他社に対して牽制する効果のない特許であれば、
有効な特許とは言えません。
ですから、拒絶理由通知の内容からは、
特許にすることが難しいと思えたとしても、
「特許を取りたいところで権利化する」という
意識をもつことが重要だと思っています。
そして、そのような、一見、克服するのが難しいと
思えるような拒絶理由通知がきたとしても、
それを克服して、特許にすることが必要となってきます。
6月6日(金)のセミナーでは、一見、難しいと
思えるような拒絶理由通知に対して、
どう対応していくのか、そのための具体的な考え方を
お伝えしたいと思っています。
http://www.lhpat.com/seminar.html
より多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
こんにちは。田村です。
前回、「拒絶理由通知への対応」についてのセミナーを
6月6日(金)に実施する、とお伝えしていました。
ご興味のある方は、以下をご確認ください。
http://www.lhpat.com/seminar.html
拒絶理由通知への対応は、実は、私が最も得意とする
テーマです。今回は、新規性・進歩性を中心にお話を
したいと考えています。
拒絶理由通知への対応の良し悪しで、特許になるか否か
が決まりますし、
対応がまずければ、たとえ、特許になったとしても、
権利範囲が狭く、有効な特許にならない可能性もあります。
特許に関する業務の中でも、非常に重要な位置を占める
ものであることは、言うまでもありません。
特許の仕事を始めて10年以上経ちましたが、
その間に、業務に携わる中で経験として学んできたことを、
分かりやすくまとめ、出し惜しみすることなく、
お伝えしたいと思います。
より多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。
http://www.lhpat.com/seminar.html
さて、本題です。
平成26年4月より、特許庁における前置報告を利用した
審尋に関する運用が改定されたようです。
前置報告を利用した審尋について(特許庁サイト)
拒絶査定不服審判の請求時に、明細書や特許請求の範囲の
補正を行った場合、審査官による前置審査が行われます。
前置審査の結果、特許にすることができないと審査官が
判断した場合は、前置審査が解除されて、審判官による
審理が開始されます。
これまでは、前置審査がなされた後、
特許にすることができないとして前置報告がされた場合は、
特許庁から審尋の機会が与えられ、60日以内に回答書で
意見を述べることができましたが、
今回の特許庁の運用改定に伴い、「医療、バイオテクノロジー
関係の技術分野」以外の分野については、審尋の機会が与え
られないこととなりました。
とは言っても、前置審査の結果に対して、
全く意見を述べることができないわけではありません。
前置審査の解除通知がされ、前置報告の内容を確認して、
意見を述べる必要があると判断した場合は、
自発的に上申書を提出することで、意見を述べることができます。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
こんにちは。田村です。
実は、6月6日(金)に、
都内でセミナーを企画しております。
テーマは「拒絶理由通知への対応」についてです。
以前も実施をしておりましたが、内容の見直しをして、
再開したいと考えています。
まだ、申込みページ等の準備ができておらず、
正式な告知は、来週となりそうです。
ご興味のある方は、6月6日の午後の予定を
空けておいてくださいね。
さて、本題です。
請求項を記載するとき、権利範囲ができるだけ、
広くなるように記載したい、というのは、
誰しもが思うことです。
気を付けないといけないのは、
油断をしていると、実施例の記載につられてしまい、
請求項の記載が、必要以上に狭くなってしまうことです。
単に、実施例を上位概念化しただけでは、
発明の本質をとらえた権利範囲とならない場合があります。
例えば、「円柱状の鉛筆」が有する、転がりやすいという
問題を解消するために「六角柱状の鉛筆」を発明した場合、
「六角柱状の鉛筆」を上位概念化したとしても、
「多角柱状の鉛筆」とはなりますが、
それ以上、上位概念化することは、できないでしょう。
例えば、
「楕円柱状の鉛筆」でも「円柱状の鉛筆」に比べて、
転がりにくくなりますから、課題を解決することはできます。
しかし、「多角柱状の鉛筆」の権利範囲には含まれていません。
では、どのように上位概念化するべきかですが、
「発明の効果」が得られる根本的な理由、要因は何か?
を考えることが重要だと思います。
鉛筆の例について、私なりの結論ですが、
転がった時に重心の高さが変化することが、
鉛筆が転がりにくくなる本質的な理由ではないか?
と思います。
それを考慮したうえで、請求項を記載すると、
「柱状であり、
長さ方向に垂直な断面における重心から
断面の外周までの距離が不均一である、鉛筆。」
などの記載が考えられます。
「発明の効果」が得られる根本的な理由、要因を
明確にすることで、実施の形態につられることなく、
請求項を記載することができます。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。