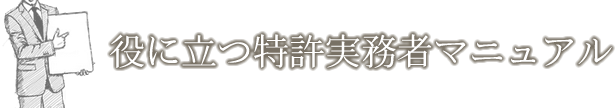こんにちは。田村です。
日常の会話で、こんなことありませんか。
Aさん「○○について・・・・・だと思うんだけど」
私「それは違うよ。○○は・・・・・だよ」
Aさん「ムスっ、、、」
コミュニケーションについての書籍を読むと、
相手とは異なる意見を述べる場合でも、
まずは、相手の意見を受け入れてたうえで、
自らの意見を述べると、
コミュニケーションが円滑に進みやすいそうです。
私「Aさんの○○は・・・・・だという意見は、
よくわかります。ただ、私は、この点だけ、
違う意見です。」
みたいな感じでしょうか。
私は正直なところ、全然できておりません(汗)。
まずは、相手の意見を理解し、尊重する姿勢が
必要なのでしょうね。
身近な人になるほど、いきなり否定から入る
ような会話になりがちです。
気を付けていきたいものです。
さて、本題に入ります。
特許庁から拒絶理由が通知されると、
意見書、手続補正書を提出して
対応することができます。
中には、拒絶理由通知書を読んでも、
審査官がなぜそのような判断をしたのか、
その真意がよく分からないことがあります。
そんなとき、
審査官は何か大きな勘違いをしている、
審査官はこの発明のことをよく理解していない、
と考え、
「審査官殿の判断は妥当ではありません。・・・ 」
と意見書で主張しても、うまくいきません。
審査官が何か大きな勘違いをしている、
と思った時は、
自分が審査官の真意をよく理解できていないだけで、
自分自身の方が勘違いをしている、
ということを疑ってみるべきです。
先ほどの日常会話と同じで、
まずは、審査官の真意を理解できるまで、
繰り返し繰り返し、
拒絶理由通知書、明細書と、
にらめっこをした方が、
良い結果につながります。
審査官の真意が理解できて、
審査官の言うことも一理ある、
くらいに思えたときに、はじめて、
審査官にも、その発明の特許性を十分に
納得してもらえる、
適切な意見書を書くことができるように思います。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
———————————————————-
こんにちは。田村です。
事務所の近くに、
厨房のフライパンの音が聞こえてくる
活気のある中華料理店があります。
以前、この中華料理店で、
チンジャオロースを注文したのですが、
驚くべきことが、起こりました。。。
店員さんが、厨房に向かって、
「ピーマン1つ!!!」
自分の耳を疑いました。。。
「ちゃんと、チンジャオロースって言ったよね?」
「ピーマンは頼んでないし(泣)、、、」
「ピーマンがまるごとでてきたら、どうしよう?」
そんなことが、頭の中をぐるぐる。
5分後、9割がピーマンの炒め物がでてきました。
そりゃ、「ピーマン1つ!!!」って言うよね、
という感じでした(笑)
あ、でも、おいしかったですよ。
このように(?)、
外部には通用しない、社内用語なるものが、
多くの組織で使用されていたりします。
その影響かどうかは定かではありませんが、
特許明細書でも、一般的には使用されない、
造語などが用いられていることがあります。
このような造語は、意味が不明確になりますので、
明細書の中で使用することは、避けたいものです。
例えば、
辞書に載っているような一般的な用語でも、
このような用語同士を結合させて使用すると、
意味が不明確になることがあります。
「ねぎ」と「麺」という用語は、
それぞれ、多くの辞書に掲載されていますし、
その意味は明確です。
ですが、これをくっつけて、「ねぎ麺」とすると、
「ねぎのエキスを練り込んだ麺」なのか、
「ねぎがたっぷりかかった麺料理」なのか、
それとも、、、
といったように、
たちまち、意味が不明確になります。
明細書を書く際は、
このような造語を使用することなく、
一般的に用いられている単語や技術用語だけで、
文章をつくることを意識する必要があります。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
———————————————————-
こんにちは。田村です。
先日、事務所の近くの飲食店で、
夕食をとったのですが、
大変恥ずかしい思いをしました。
すでに半分以上、料理を食べてしまった頃に、
ふと、気がついたのです。
そういえば、財布の中に、あまりお金が
はいってなかったような。。。
あわてて数えてみると、
100円程足りませんでした(泣)。
大きな出費の後だったので、
気をつけるべきでした。
店員さんに事情を話し、
「すぐに戻ってきて、料金を支払います」
と言ったところ、
「いつも来ていただいているので、いいですよ」
とご快諾いただきました。
顔を覚えてもらっていて、よかったです。
さて、本題です。
今日は、早期審査の話です。
特許庁の統計によると、
2011年の実績で、
審査請求をされてから、審査結果の最初の
通知がされるまでの期間が
平均して25.9ヶ月だそうです。
特許になるまでに、2年以上かかります。
ただし、早期審査制度を活用すれば、
この期間をぐっと短くすることができます。
審査結果が最初に通知されるまでの期間を
平均して約1.8ヶ月まで、
短縮することができます。
早期審査制度を利用できるのは、
以下のいずれかに該当する出願となります。
1.中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
その発明の出願人が、中小企業又は個人、大学など
である場合です。
中小企業に該当するかどうかは、
従業員数や資本の額等を基準として判断されます。
2.外国関連出願
出願人がその発明について、日本の特許庁以外の
外国の特許庁等へも出願している場合です。
PCT出願をしている場合でも、大丈夫です。
3.実施関連出願
出願人又はその発明について実施許諾を受けた者が、
その発明をすでに実施している、或いは、2年以内に
その発明を実施する予定がある場合です。
4.グリーン関連出願
グリーン発明(例えば、省エネ、二酸化炭素の削減
に関する発明)についての特許出願の場合です。
5.震災復興支援関連出願
出願人の事業所等が地震に起因した被害を
受けた場合であって、
その事業所等でされた発明、又は、
その事業所等で実施される発明の場合です。
少しでも早く権利化をご希望される場合は、
是非、ご活用ください。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
———————————————————-
こんにちは。田村です。
最近、『「続ける」技術』(著:石田淳)
という本を読んでいます。
何事においても3日坊主が多い私ですが、
「こんどこそは」
という意気込みで、読んでおります(笑)。
読んでいて、非常に印象的なのは、
物事を継続できないのは、
意志が弱いからではない、
ということ。
「続ける」技術を身につければ、
三日坊主とおさらばできるのかもしれません。
ご興味の或る方は、是非、ご一読ください。
さて、本題です。
今日は、出願審査請求の話です。
日本の特許制度では、特許出願をしてから、
3年以内であれば、
出願審査請求をすることができます。
審査請求をすることで、審査が開始されます。
ただ、特許庁でも膨大な数の特許出願について
審査をしているため、
審査請求をしてもすぐに審査が開始される
わけではありません。
特許庁の統計によると、2011年の実績で、
審査請求をされてから、審査結果の最初の通知が
されるまでの期間が
平均して25.9ヶ月だそうです。
つまり2年以上かかるわけです。
そこで、どのタイミングで審査請求をするか
が問題となります。
すぐにでも製品化する可能性がある場合や、
製品のライフサイクルが短いものについては、
出願から3~4年も経過してから権利化が
されても遅いわけですから、
出願と同時に、そうでなくても、
できるだけ早期に審査請求をすることが
望ましいといえそうです。
一方、優れた発明ではあるけれど、
現段階では、製品化されるかどうかが
分からない場合や、
先願の状況を見極めたい場合など、
中長期的にその発明の価値を評価していく
必要があるときは、
出願から1年半~3年が経過するまでに、
審査請求をするのが、
適切だといえそうです。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
———————————————————-
こんにちは。田村です。
先日、知人からドイツで販売されている
缶ビールをお土産でいただきました。
そんなに大きな期待はせず、
何気なく飲んでみたのですが、
これが、ほんとにおいしくて、びっくりでした。
苦味がなくて、フルーティーな感じ、
というのでしょうか。
このおいしさを文章でお伝えすることが
難しく、残念です。
味の宝石箱や~(古いですか)
みたいな表現を思いつきません(笑)。
このビール、フランチスカーナー・ヘーフェヴァイス
という銘柄なのですが、
ヴァイスビールの中でも、1、2を争うほど、
有名なものらしいです。
調べてみると、事務所の近くに、
フランチスカーナーの名前を冠するお店がありました。
是非、近日中に、行きたいと思っています。
さて、本題です。
先日は、特許法第39条の先願主義の
規定についてのお話でした。
二つの出願の請求項に記載された内容が
異なっていても、
一方の発明の発明特定事項が、
他方の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術の
付加、削除、転換等を施したものに相当し、
且つ、新たな効果を奏するものではない場合は、
発明が実質的に同一だと判断されます。
この拒絶理由について、どのような対応を
とることができるかですが、
まず、1つ目です。
請求項を補正せずに、反論します。
二つの出願の請求項の相違している点が、
周知技術、慣用技術ではないことを説明します。
2つ目です。
同じく請求項を補正せずに、反論します。
二つの出願の請求項の相違している点をもとに、
新たな効果があることを説明します。
この両方を併せて、反論することも可能です。
そして、上の2つのいずれでも、
反論することが難しそうな場合は、
3つ目です。
引用例の請求項とは、別の発明となるように、
請求項を補正することが考えられます。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
———————————————————-