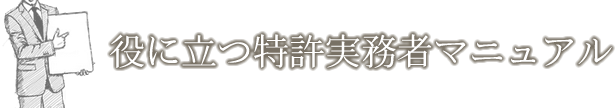こんにちは。田村です。
配信に少し、間が空いてしまいました。
普段、小説はあまり読まないほうなのですが、
司馬遼太郎さんと、東野圭吾さんの小説は、
かじる程度ではありますが、読んでいます。
全然、ジャンルが違いますね(笑)。
先日、司馬遼太郎さんの「太閤記」を読んだ
のですが、面白くて、一気に読んでしまいました。
おかげで、豊臣秀吉という人物の大ファンに
なりました。
一番印象的だったのは、
「秀吉の合戦は、敵を見たときにはもはや合戦の
ほとんどがおわっていた。あとは勝つだけであった。
(戦さとは、そうあらねばならぬ)
そう思っている。戦さは勝つべき態勢をつくり
あげることであった。」
という箇所。
これは、何も戦さだけに限らず、
ビジネスでも同じで、「勝つべくして勝つ」という
状況を目指すべきなんでしょうね。
「勝つべくして勝つ」という状況をつくるための
一つの手段として、特許があるのだと思います。
さて、話は変わりますが、
分割出願をしたときに、よくだされる拒絶理由の
一つとして、
特許法第39条の先願主義の規定があります。
この先願主義の規定ですが、
分割出願の親出願と子出願のように、同じ日に
同一の発明について出願がされた場合にも、
特許を受けることができない、とされています。
ここで、問題となるのが、
同一の発明であるかどうかの判断です。
親出願と子出願に、全く同一の内容の請求項が
ある場合だけでなく、
請求項の記載内容が違っていても、
実質的に同一の発明と考えられる場合は、
特許法第39条の拒絶理由の対象となります。
実質的に同一の発明であると考えられる
ケースとして、最もよくあるケースが、
二つの出願の請求項に記載された内容が
異なっていても、
一方の発明の発明特定事項が、
他方の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術の
付加、削除、転換等を施したものに相当し、
かつ、新たな効果を奏するものではない場合
があげられます。
つまり、二つの出願の請求項の記載内容に
違いがあっても、
その違っている部分が周知技術等であり、且つ、
その周知技術等を付加などすることによる効果も、
特に認められないときに、
二つの発明は同一の発明であると判断されます。
この拒絶理由については、どのような対応が可能でしょうか。
続きは、次回にて。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
———————————————————-
こんにちは。田村です。
少し遅くなりましたが、
本年もよろしくお願いします。
気がつけば、メルマガの更新が一ヶ月ほど、
あいてしまいました。
言い訳になりますが、
今週の月曜日に新しい事務所に移転しまして、
その準備と、年末の忙しさもあり、
このような結果となりました。
本年も引き続き、メルマガを配信して
まいりますので、
よろしくお願いいたします。
今年、最初の話題は、
新規性喪失の例外についてです。
平成23年の特許法の改正で、
新規性喪失の例外規定が適用される
範囲が広がりました。
新規性喪失の例外規定とは、
本来であれば、新規性を失ったと
判断される行為であっても、
所定の条件を満たせば、
新規性を失っていないとの
例外的な取り扱いをするというものです。
従来は、
刊行物への発表、インターネットを通じて
の発表、所定の学会での文書発表など、
所定の行為だけが、この規定の適用の対象と
されていましたが、
平成23年の法改正により、
テレビ・ラジオ等で公開された発明や
販売によって公開された発明なども
適用の対象となるように改正されました。
ですから、製品の販売を行った後に、
特許出願をすることも可能となります。
このように便利な新規性喪失の例外規定
ですが、
気をつけないといけないことがあります。
というのも、日本ではこのような規定が
ありますが、
必ずしも諸外国で、同じような制度が
認められるわけではないということです。
例えば、
ヨーロッパ特許庁へ出願をするような場合、
このような新規性喪失の例外規定は
ありませんから、
当然、販売等を行った後に特許出願をしても、
特許を受けることができなくなります。
ですから、
外国へ出願する可能性がある場合は、
やはり、販売等を行うまでに、特許出願を
行う必要があるということになります。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
———————————————————-