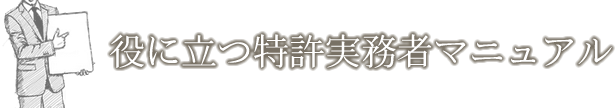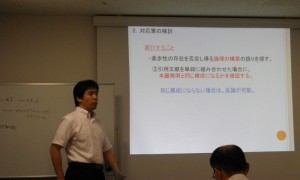こんにちは。田村です。
先日、インターネットのニュースで、
「勝率100%のじゃんけんロボット」が開発されたとの
ニュースが掲載されていました。
東京大学の情報理工学系研究科で開発されたもので、
ロボットは指で、グー、チョキ、パーをだすそうです。
なぜ、100%でじゃんけんに勝てるかというと、
ヒトの手の画像を1000分の1秒ごとに認識し、
相手が何を出すのかを、瞬時に判別しているようです。
ロボットは、グー、チョキ、パーのどれかのうち、
相手に勝てるものを選択して、ヒトが手を出した
1ミリ秒後に、手をだすそうです。
後出しだと気付かないほどの超高速で、
後出しじゃんけんをするということです。
いや~、おもしろいですね。
それでは、本題です。
特許出願の後、審査が開始されると、
特許庁から、発明に進歩性がないとして拒絶理由通知が
届くことがあります。
拒絶理由通知の内容を読んでみると、複数の引用文献を
組み合わせて進歩性がない、とのこと。
どう対応するべきか、悩むわけですが、
こんなときに、非常に便利な方法があります。
それは、発明の内容を全く知らなかったと仮定して、
拒絶理由通知で引用された文献を組み合わせて、
発明をすることができるだろうか?
と考えます。
すると、
発明の内容を全く知らない人であれば、
複数の引用文献を組み合わせても、その発明と同じような
ものを発明することは、難しいのでは?
と気づくことがあります。
審査官は、発明の内容を知っているから、簡単に、
進歩性がないと言えるわけで、
実際には、そんな簡単に発明できるものではありません。
つまり、審査官は「後出しじゃんけん」しているので、
それを見破れば、特許になる、ということです。
じゃんけんロボットの後出しを見破ることは、至難の業ですが、
審査官の後出しであれば、もう少しハードルが低くなります。
あとは、
なぜ、複数の文献を組み合わせても、その発明と同じような
ものを発明することが難しいのか、その理由を考えます。
この理由が反論の切り口になります。
是非、お試しください。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
こんにちは。田村です。
少しご無沙汰しておりました。
さて、よくあるご相談の一つとして、
特許出願前に、試作品を外部に提供したり、
製品を販売してもいいですか?
というものがあります。
ご存知のように、特許出願をする前に、
発明品を試作品として第三者に提供したり、
製品として販売すると、発明の新規性が失われます。
そのため、発明品を外部に提供する前に特許出願を
することが必要になります。
ただ、特許出願前に試作品として発明品を外部に
提供する場合でも、
試作品の提供先と秘密保持契約を結んでいれば、
新規性は失われないことになります。
簡単に言うと、
秘密保持義務を負っている第三者に対しては、
特許出願前に発明品を提供したとしても、
発明の新規性が失われることはありません。
また、仮に特許出願をするよりも前に、発明品を試作品
として第三者に提供したり、製品として販売したとしても、
「新規性喪失の例外規定の適用」の手続を行えば、
特許出願前のこれらの行為をもとに、新規性が失われる
ことはなくなります。
この非常に便利と思える「新規性喪失の例外規定の適用」
ですが、弱点としては、外国に出願をする場合です。
国によっては、このような特別な取扱いもなく、
特許出願より前に、発明品を外部に提供すると、
新規性が失われ、特許が認められなくなる場合もあります。
ですから、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合は、
将来的に外国出願をする可能性があるのか?、
どこの国へ出願するのか?
等を十分に考慮したうえで、判断する必要があります。
発明品について外部に公表する前に、余裕をもって特許出願を
しておくのが、当然のことではありますが、ベストです。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
———————————————————-
平素は弊所サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
弊所では下記の日程を本年度の夏季休暇とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
■夏季休暇期間
2014年8月13日(水) から 2014年8月15日(金) まで
※ 上記期間中もインターネット経由でのお問い合わせは受け付けておりますが、
2014年8月18日(月)以降の対応とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
今後とも、格別のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。
こんにちは。田村です。
暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
事務所では、エアコンのお世話になっていますが、
温度を下げすぎると、体によくありません。
うちの事務所では、小型の扇風機を活用して、
空気が対流するようにしています。
そうするだけで、エアコンの温度をそれほど
下げなくても、快適な空間が作れます。
さて、本題です。
特許請求の範囲や明細書を補正するとき、
どこまでの補正が認められて、
どこまでの補正が認められないか、
迷うことはないでしょうか。
補正の認められる範囲ですが、
「出願時の明細書等に記載した事項」であれば、
補正が認められることになっています。
特許庁の審査基準によると、
「出願時の明細書等に記載した事項」とは
「出願時の明細書等に明示的に記載された事項」
だけでなく、
「出願時の明細書等の記載から自明な事項」
も含まれます。
この「自明な事項」をどう解釈するのか、
非常に難しい問題です。
特許庁の審査基準によると、
「補正された事項が、「当初明細書等の記載から自明な事項」
といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、
これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、
その意味であることが明らかであって、その事項がそこに
記載されているのと同然であると理解する事項でなければ
ならない」
とあります。
つまりは、当業者であれば、
誰が見ても明細書に記載されているも同然である、
と言えるような事項でないかぎりは、補正は認められない
ということです。
明細書に明示的に記載されていない事項で
補正したとしても、
実際には、それほど簡単には認められません。
明細書に明示的に記載されていない事項を
追加する補正が可能な場合もありますが、
できれば、
明細書に明示的に記載されている事項で
補正をする方が良いことはいうまでもありません。
明細書を作成するにあたっても、
将来的に補正をすることができるかを考慮しながら、
明細書を記載していくことが好ましい、といえます。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。