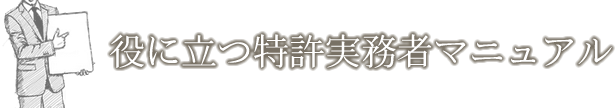こんにちは。田村です。
最近、「嫌われる勇気」という本を読みました。
フロイト、ユングと並んで「心理学の三大巨頭」と
称されるアルフレッド・アドラーの心理学を、
対話形式で、紹介するものです。
読んだ感想ですが、より良く生きていく
ためのヒントが得られる本だと思います。
本書によると、
「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」
とのこと。
悩みの全てが対人関係というのは少し極端かも
しれませんが、多くの悩みが対人関係に起因する
というのは、その通りだと思います。
私が印象に残ったのは、
「対人関係のなかで「わたしは正しいのだ」と
確信した瞬間、すでに権力争いに足を踏み入れている」
「対人関係のカードは常に「わたし」が握っていた」
との記載です。
対人関係で何らかの摩擦が発生したとき、
ついつい、自分ではなく、相手方に原因を
求めてしまうことがあります。
ただ、無理やり相手を変えることはできませんから、
「私が正しく、相手が間違っている」と批判するのではなく、
「カード」を握っているのは自分なのだから、
自分ができること、変えれることに意識を向け、
状況を改善していく、ということなのかもしれません。
実践するのは、簡単なことではありませんが、
意識をするだけでも、変わってくる、
そんな気がします。
対話形式ですから、専門書のように難しくもなく、
気軽に読めます。
お薦めの一冊です。
さて、本題です。
請求項の記載で
「A、B及びCからなる組成物」といったように、
「からなる」という表現を用いることがあります。
この「からなる」ですが、特許権の権利範囲を
解釈するうえで、問題となることがあります。
つまり、A、B、Cのみが含まれ、それ以外の成分が
含まれる場合は、権利範囲外であると解釈するのか、
或いは、A、B、C以外の成分が含まれている場合も、
権利範囲内であるのか、ということです。
過去の裁判例では、
明細書内に、他の成分が含まれても良い、といった
記載がされているような特別の事情がある場合は、
その他の成分が含まれていても権利範囲に入るが、
そのような事情がない場合は、A、B、Cのみが
含まれている場合だけ、権利範囲内とする、
と判断されているようです。
ただ、権利範囲の解釈について、争いの余地が
残されるのは、あまり好ましくありませんので、
「からなる」という記載ではなく、
「A、B及びCを含有する組成物」、
「A、B及びCを含む組成物」
といったような表現を用いた方が良いと思われます。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
こんにちは。田村です。
今日は、新規性や進歩性の拒絶理由通知が出された場合
における補正案の検討についてです。
引用文献に記載された内容が本願発明に近い場合など、
請求項を補正しなければ、拒絶理由を覆すことができない、
と考えられるようなケースがあります。
ただ、本願の請求項と、引用文献の記載と、
にらめっこをしても、どのように補正をすべきかについて、
なかなか良いアイデアが浮かばない場合があります。
そんなときの良い方法として、
本願明細書の実施例と、引用文献の実施例を比較する
という方法があります。
例えば、組成物の発明について、
本願明細書と引用文献の実施例を比較した時に、
ある化合物の含有量が大きく違うことが発見できたとします。
そうすると、請求項を、この化合物の含有量の範囲で
限定する補正をすることで、
本願発明の特許性を主張することが可能となる場合があります。
請求項をどんどん下位概念化したときの最も下位の概念に
あたるのが、本願明細書の実施例です。
まずは、本願と引用文献との間で、実施例レベルで違いを
見つけることができれば、
請求項をどのように補正すれば良いかのヒントが得られます。
是非、お試しください。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
こんにちは。田村です。
このメールマガジンを発行するのも、
実は今日で100号目です。
約3年前に始めたのですが、
その間、発行が途切れた期間もありました。
それでも、「100」という数字はうれしいですね。
今後もしっかりと継続して、200号、300号を目指します。
さて、本題です。
平成26年4月(来月)から、産業競争力強化法に基づく
特許料等の軽減措置により、特定の対象者について、
日本国内にした特許出願についての審査請求料・特許料、
PCT出願についての調査手数料・送付手数料・予備審査手数料
が1/3に軽減されます。
平成26年4月から平成30年3月までに、
審査請求又はPCT出願を行った案件に限られます。
特許料については、上の期間内に審査請求を行った
出願のみが軽減の対象となりますので、
平成30年3月以降に、特許料を支払う場合にも適用されます。
特許されてから10年までに支払う特許料(年金)のうち、
10年目の特許料は6万円以上になりますから、
これが1/3に軽減されると、かなりの減額となります。
軽減措置の対象者は、以下の通りです。
1.小規模の個人事業主
(従業員20人以下(サービス業は5人以下))
2.事業開始後10年未満の個人事業主
3.小規模企業(従業員20人以下(サービス業は5人以下))
4.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
ただし、小規模企業や資本金3億円以下の法人であっても、
大企業の子会社の場合は、認められません。
申請方法ですが、各種手続きを行う際に、軽減申請書と、
軽減措置の対象者に該当することを証明する書面の提出が
必要となります。
是非、ご活用ください。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
こんにちは。田村です。
冬季オリンピック、終わりましたね。
期間中は、たくさんの感動をいただきました。
私は、浅田真央選手のフリースケーティングの演技が、
すごく印象に残りました。
皆さんは、いかがでしたか。
さて、本題です。
前回は、論理の飛躍がないように、文章を書きましょう、
というお話をさせていただきました。
「AだからCである」といったように、
Aという事実からCという結論にいきなり飛ぶのではなく、
「AだからBである。よって、BだからCである。」
といったように、
Aという事実からBという事実や予想を導き出し、
Bという事実や予想からCという結論を導き出すことで、
論理の飛躍を防ぐことができます。
例えば、以下のような場合を考えてみます。
本願発明の請求項
「樹脂A、樹脂B及び架橋剤Cを含む接着剤組成物」
引用文献1
「樹脂A及び樹脂Bを含む接着剤組成物」
拒絶理由通知の内容
「引用文献1には、架橋剤Cを用いることは記載されて
いないが、接着剤の分野において、架橋剤Cを用いる
ことは、周知である。
よって、引用文献1において接着剤Cを用いることは、
当業者が容易に想到し得る事項であり、本願発明は、
進歩性を有しない。」
このような場合に、意見書において、
「樹脂A、樹脂B及び架橋剤Cを含む組成物の接着性
試験の結果は「10」ですが、樹脂A及び樹脂Bを
含む組成物の接着性試験の結果は「2」であり、
本願発明は、予想もできない優れた効果を有します。」
と主張したとします。
ですが、樹脂A及び樹脂Bに、架橋剤を添加すれば、
接着力が向上することは十分に予測できますので、
本願発明が、予想もできない効果を有すると言えるか?
というと微妙な気がします。
次のような場合は、どうでしょうか。
「樹脂A、樹脂B及び架橋剤Cを含む組成物の接着性
試験の結果は「10」ですが、樹脂A及び樹脂Bを
含む組成物の接着性試験の結果は「2」です。
また、樹脂Aのみに架橋剤Cを添加した場合は、
接着性試験の結果は「3」であり、
樹脂Bのみに架橋剤Cを添加した場合も、同様に、
接着性試験の結果は「3」となります。
樹脂Aや樹脂Bに架橋剤Cを添加することで、
接着力は向上しますが、接着力が「1」だけ
向上するのみです。
しかし、樹脂A及び樹脂Bの両方が存在する場合に
架橋剤Cを添加すると、接着力は「8」も向上する
ことになります。
仮に、架橋剤Cを用いることで接着力が向上する
ことは予測できたとしても、このように大幅に接着力
が向上することは、当業者が予想できることでは
ありません。
よって、本願発明は、予想もできない優れた効果を
有するものであることが分かります。」
後者は、前者と異なって、
本願発明が予想もできない効果を有すると判断できる
だけの材料がそろっており、
単に試験結果を数値で記載しただけでなく、
そこから導き出される「接着力の向上する度合い」から、
結論へと移行しています。
何かの結論や主張を述べようとする際には、
その結論や主張を支えるための根拠や理由が必要ですし、
その根拠や理由を、順を追って丁寧に説明していくことで、
論理の飛躍がない、説得力のある意見や主張となります。
———————————————————-
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
2013年11月にカスタマワイズよりインタビューを受けました。
詳細はこちら