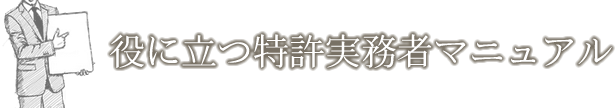こんにちは。田村良介です。
先日、おもしろいお店を発見しました。
キャンディをラッピングしてブーケのようにしたキャンディブーケの専門店です。
店内はキャンディブーケで埋まっていて、見ているだけで、楽しい気分になってきます。
ブーケに使われているキャンディ、チョコレート、ラムネなどは、数十個ですが、
これがブーケになると、すごく華やかになります。
誕生日やお祝いごとなど、ちょっとしたプレゼントなどに、最適だと思います。
このキャンディブーケ、
原価はそれほどかかっていないのではないかと思うのですが、
価格は数千円。
キャンディ+ブーケ
という発想で、新しい価値を生み出した、すばらしい商品ではないかと思います。
この新しい発想について、特許を取得することはできるでしょうか。
さすがに、
キャンディ+ブーケ
というコンセプトだけで、特許性が認められるのは、難しいかもしれませんが、
キャンディをラッピングするための何らかの工夫が、もしあるようであれば、
その工夫で、特許を取得することが考えられます。
大きな概念で特許を取得できなくても、
その概念を実現するにあたっての工夫で特許を取得することができれば、
仮に、他社が同じようなことを始めたとしても、優位性を保つことができます。
同じことが、ビジネスモデル関連のアイデアでも言えます。
例えば、ピザの宅配ビジネスで、
注文してから30分以内に届けなければ、ピザを無料にする、
ことを考え付いたとします。
ビジネスモデルそのものは、特許の対象とはされていません。
ただし、このビジネスモデルを実現するために工夫できることは、
たくさんあるのではないか、と思います。
ピザをはやく焼き上げるために、生地、ピザの形状、釜などを工夫したり、
ピザを効率的に配達するために、
どの配達先に、どの順番で配達するかを計算するシステムを開発したり・・・。
ビジネスアイデアそのものは特許になりませんが、
ビジネスアイデアを実現する際の工夫であれば、特許の対象となります。
こうした工夫で特許を取得することができれば、
他社が同じようなビジネスは始めたとしても、自社の優位性を保つことができます。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆アイデアそのものが特許の対象ではなくても、
そのアイデアを実現する際の工夫であれば、特許の対象となる。
☆アイデアを実現する際の工夫について、特許を取得することで、
自社の優位性を保つことができる。
————————————————————————
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————
平素は弊所サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、弊所では下記の日程において、年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
■年末年始休業期間
2016年12月29日(木) から 2017年1月3日(火) まで
※年末年始の休業中も、インターネットからのお申し込みは受け付けておりますが、
12月29日以降のご連絡に対するお返事は、緊急の場合を除き、
2017年1月4日(水)以降となる場合がございますので、
あらかじめご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
今後とも、格別のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。
こんにちは。田村良介です。
以前、読んだ本にこんなことが書いてありました。
ある島にたどり着いた、2人の携帯電話のセールスマンがいました。
一人は
『ここでは誰も携帯電話を使っていない。飛行機ですぐに帰る。』
と、本国に連絡をいれました。
もう一人は
『ここでは誰も携帯電話を使っていない。すぐに携帯電話を5万台、送ってほしい』
と、本国に連絡をいれました。
おもしろいもので、同じ出来事でも、人によって、解釈は大きく異なります。
前者は、売上をあげることができませんが、
後者は、すばらしい営業成績をあげることができたかもしれません。
この2人の職業はセールスマンですから、
後者の方が、セールスマンとして適切な解釈をしているのでしょうね。
出来事をどのように解釈するかは、その人次第ですが、
できるだけ、自分にとってプラスになるような解釈をしていきたい、
この話を読んだときに、
そんなことを思ったのを覚えています。
振り返ってみると、
特許の世界でも、同じようなことがあります。
特許要件の1つである進歩性についてですが、
進歩性を有しているかどうかの一つの判断基準として、
先行技術と比べた有利な効果があるか、
というものがあります。
例えば、普通に考えると有利な効果がない、
と思えるような技術について、考えてみます。
従来品よりも強度がない素材は、
『強度』という点では劣っています。
ですが、もしかすると、
『柔軟性』という点では優れているかもしれません。
従来品よりも透明性がないフィルムは、
『透明性』という点では劣っているかもしれません。
ですが、もしかすると、
『隠ぺい性』という点では優れているかもしれません。
見方を変えることで、効果がないと思われるものでも、
効果を見出すことができることがあります。
では、従来品よりもコストダウンしたもので、
従来品と同等の性能を有する製品は、どうでしょうか。
コストダウンは技術的な効果ではありませんので、
コストダウンしたことを正面から主張しても、
進歩性の主張としては弱いでしょう。
ただ、見方を変えて、
従来はコストダウン品では必要な性能が得られなかった
↓
発明によりコストダウン品でも、
従来の高級品と同等の性能を得ることができた
ということであれば、
従来の性能の悪いコストダウン品と比べて、
技術的に優れたものである、
ということもできます。
出来事は解釈しだい、
発明も解釈しだい、
ということかもしれません。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆一見、すぐれた効果を有さないように思えるものでも、
解釈次第では、発明の効果を見出すことができる。
————————————————————————
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————
こんにちは。田村良介です。
先週末にオフィスの移転作業を行いまして、
本日から新しいオフィスで業務です。
これまでより広いオフィスになり、
今はまだ、広々としていますが、
数年後には、ここも手狭になってきた、
と思えるように、頑張っていきたいと思います。
さて、「7つの習慣」という書籍をご存知でしょうか。
日本国内で130万部以上、全世界で2000万部以上を
売り上げたベストセラーです。
いわゆる自己啓発書なのですが、
個人、家庭、仕事などの人生すべての側面で
活用できる、7つの習慣を紹介するものです。
7つの習慣は、以下のようなものです。
第一の習慣 主体性を発揮する
第二の習慣 目的を持って始める
第三の習慣 重要事項を優先する
第四の習慣 Win-Winを考える
第五の習慣 理解してから理解される
第六の習慣 相乗効果を発揮する
第七の習慣 刃を砥ぐ
仕事上で「Win-Win」という言葉が
使われることがよくありますが、
この「7つの習慣」で広まったものではないかと。
私が社会人になりたての頃に、
仕事も、上司との関係もうまくいかず、
悩んでいた時期があったのですが、
その時期に、この本を読んで、
私自身、かなりの影響を受けた本でもあります。
ところで、
第五の習慣の「理解してから理解される」ですが、
人間関係を改善するための習慣として
あげられたものです。
相手のことを理解しようとせずに、
自分の主張をするだけでは、
相手に自分のことを理解してもらうこともできません。
相手のことを理解するからこそ、
自分のことを理解してもらえる土壌ができます。
私自身ができているとは、とてもとても言えませんが、
そうありたいと思っています。
なぜ、第五の習慣についてご紹介したのかというと
この習慣、特許の仕事にもあてはまるんです。
拒絶理由通知がだされたとき、
「審査官が何かおかしなことを言ってるなぁ」
と感じることがあります。
重要なのは、
審査官が何かを誤解していると感じたときに、
なぜ審査官が誤解しているか、
その理由を自分が理解できているか?
ということ。
審査官が誤解していると思いきや、
審査官の指摘が妥当であることに
気付いていないだけかもしれません。
うちの事務所の皆さんにも、
このことは、口酸っぱく言っています。
「審査官の言っていることがおかしいと思ったら、
自分の理解が間違っているのでは?」
と、自分自身の理解を疑うべきだと。
審査官の指摘の真意を理解せずに、
こちらの主張だけをしても、
的外れな反論となりますから、
当然、審査官を説得することはできません。
まずは、審査官の指摘の真意を理解すること。
そのためには、拒絶理由通知を
何度も繰り返し読むと良いかもしれません。
審査官の真意を理解することができれば、
拒絶理由通知への検討は、
7~8割、終了したも同然です。
あとは、その対応策を考えるだけです。
審査官を理解するからこそ、
こちらの主張も理解されます。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆審査官が何か誤解していると感じたときは、
自分が理解できていないだけかもしれない。
☆審査官の真意を理解するからこそ、
こちらの適切な主張ができるし、
審査官にも理解される。
————————————————————————
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————
こんにちは。田村良介です。
「ジョジョの奇妙な冒険」という漫画をご存知でしょうか。
1987年から連載されている、大ヒット漫画です。
30~40代の男性の方なら、
多くの方がご存知ではないかと思います。
私は中学生の頃から、大ファンでした。
最近も「ジョジョの奇妙な冒険 第4部」が
映画化されることが話題となっています。
先日、その作者である荒木飛呂彦さんの
「荒木飛呂彦の漫画術」という本を読みました。
本のコンセプトは、
荒木飛呂彦さんが、漫画の描き方の秘密を、
実際の作品を題材にして、包み隠さず説明する、
というものです。
読んでみて、すごくおもしろかったです。
「ジョジョの奇妙な冒険」が売れているのには、
やはり理由がある、というのが分かる本です。
印象に残ったのは、
ひとつのセリフ、ひとつの絵に、
意味や目的がこめられている、ということ。
「今日はパスタでも作ろうかな」というセリフで、
・主人公はイタリアンが好き
・自分で料理を作る人
・たぶん家族はいない。ひとり暮らし
・貧乏ではない
といった多くの情報を伝えることができる、
とのこと。
さすがに、荒木飛呂彦さんのように、
一つの文にたくさんの意味をもたせる、
ということは難しいですが、
日ごろ、明細書や意見書、お客さんへの提案書など、
大量の文章を書いていることもあり、
一文一文に目的を持たせることが、
読み手に伝わりやすい文章になるのではないか
ということは、感じていました。
例えば、意見書では、
「審査官殿は、拒絶理由通知書で・・・・と
述べられております。」
「しかし、引用文献1の【0001】では、
・・・・と記載されており、
本願発明の発明特定事項とは異なります」
「本願発明では、この発明特定事項を有する
ことにより、・・・という優れた効果を奏します」
「また、引用文献1は「・・・」を課題とするものです」
「引用文献1において本願発明の発明特定事項を採用すると、
「・・・」という引用文献1の課題を解決することは
難しくなります」
「よって、引用文献1において、本願発明の発明特定事項を
採用することは、当業者にとって、容易なことではありません」
といったように、文章を進めていきます。
1つ目の文で、審査官の判断の内容を説明し、
2つ目の文で、本願発明と引用文献1が異なることを説明し、
3つ目の文で、本願発明に優れた効果があることを説明し、
4つ目の文で、・・・
このように、
それぞれの文の目的・役割、伝えようとするメッセージが
明確に意図されているのが、
理想的ではないかと。
次の文章を書くために、この文章を書いている、
といったイメージでしょうか。
あたかも文と文がリレーで結ばれて、文章になっている、
そうすると、読みやすく伝わりやすい文章に
なるのではないかと思っています。
それぞれの文の目的・役割を意識せずに文章を書くと、
一つの文で、二つ以上のことを説明しようとして、
分かりにくくなったり、
同じことを繰り返し書いて、文章が冗長になったり、
といったことになります。
ここでは、意見書を例にしましたが、
もちろん、
メールなどで、相手に何かを伝える場面でも
活かすことができるかと思います。
とは言っても、
私もまだまだですので、
これからも精進して行きたいと思っています。
このメールマガジンはどうかって?
それは言わない約束です(笑)
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆一文一文に目的を持たせることが、
読み手に伝わりやすい文章になる
☆次の文章を書くために、この文章を書く
というイメージをもつ
————————————————————————
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————