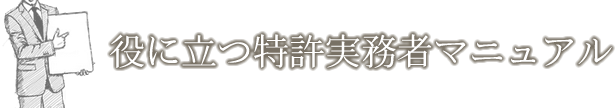こんにちは。田村良介です。
先日、NHK大河ドラマ「真田丸」が完結しましたね。
今年は、すっかり「真田丸」にはまってしまって、
毎週、欠かさず視ていました。
三谷幸喜さんの、随所にユーモアを盛り込みつつも、
緻密につくりこまれた物語の構成に、
引き込まれました。
「真田丸」の主人公は、真田信繁(幸村)です。
真田信繁は、大阪の陣の際に、豊臣方について、
徳川家康の本陣まで攻め込んだことで、
後世に「日ノ本一の兵(つわもの)」と称えられた人物です。
物語は、武田家の滅亡から大阪の陣までの
30年以上にわたる、真田家の奮闘を描いたものです。
物語の開始当初、堺雅人さん演じる真田信繁は、10代の若者。
才気はあるが、まだまだ経験も浅い若者が、
大阪の陣では、戦国屈指の名将に変貌します。
また、内野聖陽さん演じる徳川家康も、
物語の開始当初は、数いる戦国大名の一人。
大阪の陣では、老獪さに磨きがかかり、
天下人の威厳・風格がただよっています。
同じ俳優さんが演じる真田信繁・徳川家康でも、
時間の流れに応じて、成長をしています。
真田信繁という登場人物の本質的な部分を残しつつ、
見せ方、演じ方を変えることで、
人物の変化が表現されているような気がします。
俳優さんて、すごいですよね。
ところで、話は、大きく変わるのですが、
特許の世界でも、見せ方で、大きく印象が変わることがあります。
例えば、拒絶理由通知などで、進歩性を主張する場合、
実施例と比較例の実験データの結果を比較して、
発明が優れた効果を有することを示す場合があります。
例えば、
請求項が「ポリマーXと、硬化剤Yからなる組成物」であるとします。
そして、引用文献に対応する比較例が、
「ポリマーX’と、硬化剤Yからなる組成物」であるとします。
実施例の組成物から得られる成形品の強度が「30」、
比較例の場合の強度が「25」の場合、
強度の違いはあるものの、それほど大きな違いがある、
といった印象は受けません。
ですが、硬化剤を添加しない場合の強度が「24」とすると、
見え方は、全然変わってきます。
実施例の場合は、硬化剤を添加することで、
強度が「24」から「30」へと、大幅に向上しているのに対し、
比較例の場合は、硬化剤を添加することで、
強度が「24」から「25」へと、わずかしか向上していません。
硬化剤を添加することによる、
強度の向上の度合いには、相当な差があるといえます。
このように、同じ実験データであったとしても、
見せ方次第で、全く異なる見え方になる場合があります。
実験の結果をどのように見せれば、
より効果的かを考えることで、
全く違う印象を与えることもできます。
2016年のメールマガジンの発行は、今回が最後となります。
良いお年をお迎えください。
来年もよろしくお願い申し上げます。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆発明の効果を実験データで示す場合、見せ方を工夫することで、
発明の効果が優れたものであることを印象づけられる場合がある。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
2017年3月9日(木) 12:30より
株式会社 情報機構主催にて、
「ビジネス関連発明の基礎知識と保護戦略」につき
セミナーを開催いたします。
本講座では、ビジネス関連発明の事例をあげながら、
ビジネスモデルを有効に保護して、他社との優位性を
築いていくための考え方をお伝えします。
▼▼ 詳細はコチラ ▼▼
セミナーお申込み「ビジネス関連発明の基礎知識と保護戦略」
●日時 2017年3月9日(木) 12:30-16:30
●会場 [東京・東新宿]新宿文化センター4階 第2会議室
こんにちは。田村良介です。
先日、自宅近くのパン屋さんで、美味しそうなパンがないか、探していました。
すると、目を疑う商品が・・・。
といっても、パンそのものは、普通のパン。
驚くべきなのは、そのネーミングです。
そのネーミングとは・・・・
『パン・パイナップルアップル・パン』です!
『ペン・パイナップルアップル・ペン』ではないですよ。
『パン・パイナップルアップル・パン』です!
ややこしいですね。
今、大流行中のピコ太郎さんの『ペン・パイナップルアップル・ペン』。
この「ペン」の部分が「パン」で置き換えられています。
さっそく、このパンを買いました。
美味しかったです。
パンには、リンゴのコンポートがのっています。
パイナップルの味はしませんでした(笑)。
このネーミングの凄いところは、
音楽(お笑い?)という全く異なる分野のものをパンのネーミングに応用したこと。
特許業界の言葉で置き換えると、
「技術分野の関連性がない」といったところでしょうか。
もう一つ、このネーミングの凄いところは、
「ペン」→「パン」という簡単な変更ではあるけれど、
パイナップルやアップルを使ったパンであることが、消費者に伝わるということ。
特許業界の言葉で置き換えると、
「周知技術の転用」ではあるけれど、
「引用例にはない異質な効果を有する」 と表現できるのかもしれません。
というわけで、
『パン・パイナップルアップル・パン』というネーミングを特許的な視点で考えてみると、
全く異なる分野のネーミングを応用したものであり、
『ペン・パイナップルアップル・ペン』にはない、
優れた効果を有するものであると、言えそうです。
総合的にみると、このパンのネーミングは、
容易に思いつかない、進歩性のあるもの、
と言えるかもしれません。
何でも特許の業界に置き換えてしまうのは、
職業病かもしれません。
このように、
日常の出来事を、特許の視点から考えてみると、
特許の実務の訓練になるかも?
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆日常の出来事を、特許の視点から考えてみる。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
高橋利幸さんという方をご存知でしょうか。
高橋名人、と言った方が、ピンとくる方もいらっしゃるかもしれません。
高橋名人は、
ファミリコンピュータ(いわゆるファミコン)の全盛時代に、
ゲームの名人として、当時の子供たちに絶大な人気のあった人です。
私もゲーム好きな子供でしたので、高橋名人のファンの一人でした。
高橋名人の著書の中に、
『ボタンを1秒間に16回連射するには、握力や腕の力が必要』
と書いてあったので、握力を鍛えたり、腕立てをしたり・・・
ゲームを上手になるために、一生懸命になっている小学生の息子を見て、
母親は冷たい視線をそそいでいました・・・。
高橋名人の著書の中で、
もう30年以上経っているはずなのに、今も覚えていることがあります。
それは、、、、
『 ゲームを上手になりたければ、
1面をクリアーできても、すぐに2面、3面へと進むのでなく、
1面を100%の確率でクリアーできるまで、何度も1面をやり続けるといい。
1面には、そのゲームの基本的な要素の全てが含まれているから。』
というものでした。
プロ野球選手も、
いつもピッチャーをつけてバッティングをしているわけではなく、素振りもします。
松井秀喜さんが、長嶋茂雄さんの指導のもと、繰り返し素振りを練習したというのは、
有名な話です。
つまり、
物事に習熟するには、基本の徹底が重要、
ということでは、ないかと思います。
ところで、我々、特許の実務に携わる人にとっての基本とは何か?
と考えたとき、
特許庁の『特許・実用新案審査基準』の理解があげられると思います。
審査基準は、教科書みたいなものかもしれません。
でも、意外と、審査基準を読み込んでいる方は少ないのではないか、
とも思っています。
うちの事務所では、週1で、この審査基準の読み合わせをしています。
週1であっても、1年、2年と続けていくことで、
何度も審査基準と向き合うことになります。
私もこの仕事をはじめて10年以上経ちますが、
それでも、いまだに審査基準から新しい発見があります。
私が、この業界に入ったばかりのころは、
毎日、通勤電車の中で、審査基準とにらめっこをしていました。
そうやって、審査基準を読み込んでいると、仕事をしている最中に、
『審査基準のあのあたりに、今の案件と似たような状況の事例があげられていたかも』
といったことが起こってきます。
こうなると、しめたもので、
審査基準が活きた知識となってきますし、仕事のクオリティも上がってきます。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆物事に習熟するには、基本の徹底が重要。
☆特許の実務に携わる人にとって、
『特許・実用新案審査基準』の理解は、仕事をするうえでの足腰をつくるもの。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
トヨタ自動車の元副社長をされていた大野耐一さんの
『トヨタ生産方式 脱規模の経営をめざして』という書籍があります。
大野耐一さんは、トヨタ生産方式の生みの親とも呼べる方だそうです。
この書籍の中でも紹介されていますが、
大野耐一さんが提唱したと言われる考え方として、
「なぜを5回繰り返す」というものがあります。
例えば、
何らかのトラブルが発生したときに、
「なぜを5回繰り返す」ことで、トラブルの真の原因を探ることができる、
というものです。
なぜを5回繰り返さないと、すぐに思いつく答えを結論としてしまい、
表面に見える状況だけについて、対応することになります。
結局、根本的な解決はできず、
何度も問題が繰り返されることになります。
ところで、うちには、4歳の息子がいますが、
母親が叱ると言うことを聞くのに、私が叱ると、私に立ち向かってきます・・・。
『なぜ、私が叱ると、立ち向かってくるのか?』
↓
私を友達だと思っているから。
↓
『なぜ、友達だと思っているのか?』
↓
父親としての威厳を示すことができていないから。
↓
『なぜ、威厳を示すことができていないのか?』
↓
息子と一緒になって、バカな遊びをしているから。
といったように、真の原因を探りあてることができます。
それはさておき、
「なぜを5回繰り返す」ことで、
ものごとの本質を探りあてることができるのだと思います。
例えば、発明の捉え方についても、
なぜを繰り返すことで、発明の本質を探りあてることができます。
『なぜ、断面が六角形の鉛筆は、
断面が円形の鉛筆よりも転がりにくいのか?』
↓
断面が多角形だから
↓
『断面が多角形だとなぜ転がりにくいのか?』
↓
断面の中心から外周までの距離が異なるから
↓
『なぜ、中心から外周までの距離が異なると、
転がりにくくなるのか?』
↓
転がる際に、重心の高さが変わって、
水平方向に移動する運動エネルギーが、
垂直方向に移動する運動エネルギーに変換されて
消費されるから。
断面が多角形だから、という結論でとまっていた場合、
請求項は、「断面が多角形の鉛筆。」
となります。
断面の中心から外周までの距離が異なるから、という結論の場合、
請求項が、
「中心から外周までの距離が異なる形状の断面を有する、鉛筆。」
といったような感じになります。
この場合、断面が多角形以外のもの、
例えば、断面が楕円形のものも含まれます。
楕円形の鉛筆について、商業的に需要があるかどうかは別として、
『なぜ?』『なぜ?』と転がりにくい原因を追求することで、
発明の本質に近づきますし、権利範囲もより広がります。
六角形の鉛筆が転がりにくい理由として、
転がる際に重心の高さが変わる、という結論にいたった場合には、
請求項が・・・。
すみません。
大変そうなので、割愛させてください(笑)。
このように、「なぜを5回繰り返す」ことで、
発明の本質的な要素を探りあてることができるのではないか
と思います。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆発明を捉える際には、「なぜを繰り返す」。
☆「なぜを繰り返す」ことで、
発明の本質的な要素を捉えた請求項を
記載することができるのではないか。
☆結果として、より広い権利範囲の請求項を
記載することができる。
————————————————————————
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————