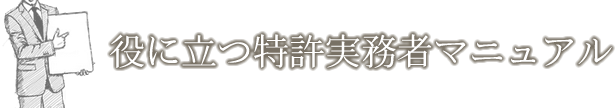こんにちは。田村良介です。
先日、事務所のスタッフA君が作成した請求項を
確認していたときのことです。
請求項を読んでみると、その意図もわかるし、
しっかり書けているように見える。
なのに、何か違和感を感じる。
どうしてだろう?
少し考え、その違和感の正体に気が付きました。
A君の作成した請求項をもとに出願しても
運がよければ、特許は認められるかもしれません。
ですが、これが原因で特許が認められない可能性も
十分に考えられました。
そして、おそらく審査官も私と同じように考える
のではないかと・・・。
私は、その違和感の正体をA君に伝えました。
「なぜ、その発明が優れた効果を得られるのかを、
十分に詰めて考えられていないのでは?」
請求項は、その発明を構成する必要最小限の構成
を記載するものです。
なぜ、その発明が優れた効果を得られるのかを
十分に把握しないままに記載をすると、
権利範囲が必要以上に狭くなるか、
本来の発明よりも請求項の範囲が広すぎるとして
拒絶理由の対象となります。
もちろん、A君も
「なぜ、その発明が優れた効果が得られるのか?」
ということを考えたうえで、
請求項を書いたのだと思います。
ただ、自分では十分に考えているつもりでも、
詰め切れていないこともあります。
コツとしては、『なぜ』を繰り返すこと。
まず、
「その発明が、優れた効果を得られるのは、
なぜだろう?」
と考えます。
優れた効果を得られる理由が見つかると、
もう一度、考えます。
「なぜ、その理由が発生するのだろう?」
このように『なぜ』を繰り返すことで、
自分では十分に考えているつもりでも、
詰め切れていない、
ということが防げるのではないかと思います。
優れた効果を得られる理由が明確になれば、
その発明を構成する必要最小限の構成も
明確になります。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆なぜ、その発明が優れた効果を得られるのか
を把握することで、
発明の本質をとらえた請求項を記載すること
ができる。
☆『なぜ?』を繰り返すことで、
なぜ、その発明が優れた効果を得られるのか
を適切に把握することができる。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
♪♪♪
風の中のすばる~
砂の中の銀河~
みんな何処へ行った~
♪♪♪
先日、家の書棚から「プロジェクトX(エックス)」
のDVDを引っ張りだしてきました。
タイトルは、
「プロジェクトX 挑戦者たち 第12巻
ツッパリ生徒と泣き虫先生」
昭和50年、当時すごく荒れていた、京都の伏見工業高校に、
元ラグビー日本代表の山口良治さんが赴任し、
それから数年でラグビー部を全国優勝に導いた、
というお話です。
伏見工業高校、山口先生をモデルにした、
「スクールウォーズ」というドラマも有名です。
私も、このドラマの影響で、
高校・大学とラグビーをしていました。
山口先生が赴任されたばかりの頃、
試合前に部員を集めるのが精一杯で、
まともな練習はできていません。
そんな中、当時、京都で一番強かった
花園高校との試合があります。
結果は、112 対 0 の大敗。
試合後、ツッパリ部員の小畑道弘が、
「俺は悔しい!」と泣き崩れます。
「先生、花園に勝たしてくれ」と
それから1年間、部員たちは必死に練習をします。
「打倒花園」の思いで。
翌年の春の京都府大会。
伏見工業高校は、花園高校と対戦します。
15人全員がチームのために走り、タックルし、攻めます。
結果、18 対 12。
伏見工業高校の勝利!
すごくないですか。
最近、涙腺が弱くなっていますので、
「プロジェクトX」を久しぶりに見て、
涙が止まらない・・・という感じでした。
さて、話はガラッと変わります。
特許庁から拒絶理由通知が届き、内容を読みます。
「ん~~、これは厳しいなぁ」
と思わず、頭をかかえることもあります。
引用文献の内容がかなり近い内容で、
特許にすることは、どうも厳しそう、、、
なのに、お客様に
「請求項の補正をした方がよいです」と提案しても、
「どうしても請求項の補正をしたくない」との回答。
ここで、もう一度、頭をかかえます。
ただ、補正をしない、
というご要望をいただいたからには、
あきらめず、知恵を絞ります。
審査官の主張に、反論できるところはないか?
拒絶理由通知も何度も読みますし、
引用文献も目を皿のようにして見ます。
そうすると、反論できるところが見つかるんですね。
審査官のわずかな隙をついて、
論理を積み上げて、意見書を書きます。
そうすると、数ヵ月後、特許査定が届きます。
そして、自分でも驚きます(笑)
伏見工業高校ラグビー部を見習って、
あきらめずに、粘り強く取り組むと、
突破口が見えてきます。
拒絶理由通知の内容が厳しいと思われるものでも、
簡単にあきらめない。粘ったもの勝ちかもしれません。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆厳しいと思われる拒絶理由通知にも、
簡単にあきらめない。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
先日、ある本を読んでいて、大発見をしました!
より読みやすく、分かりやすい文章を
作成するためのテクニックとして、
『文章を推敲する際に音読をすると良い』
ということが紹介されていました。
なんだ、そんなことか、
と思われたかもしれませんね。
でも、あなどるなかれ。
ほんとに簡単なテクニックなのですが、
効果はすごく大きいです。
よくよく考えてみると、
私自身も、文章を見直す際に、
無意識のうちに音読をしていました。
文章を目で追うだけでは、
頭の中を文章が抜けていってしまうだけで、
文章をしっかりと追いかけることはできません。
音読をすれば、目で追いかけるだけ、
という状態を避けることができます。
音読をすることで、文章を噛みしめ、
その意味を追いかけることができますから、
「て・に・を・は」の誤り、
誤字脱字、
内容や意味が分かりにくい、
一つの文が長くなりすぎている、
読み方によっては、複数の意味にとれてしまう、
などなど、
文章の至らないところに、
より確実に気付くことができます。
もちろん、それだけでなく、
説明が不足している、
説得力が足りない、
文章に迫力が欠けている、
などにも気が付くことができます。
気が付けば、あとは改善をするだけです。
実は、この「気が付く」ということが難しかったりします。
もちろん、仕事をしている最中に音読をすると、
周囲の方にも迷惑になってしまうかもしれません。
そういった場合は、小さくつぶやく、
あるいは、心の中で読むということで、
いいのではないかと思います。
メールを書くにも、明細書や意見書を書くにも、
役立つテクニックだと思います。
もちろん、このメールマガジンも
何度も音読したのですが、大丈夫でしょうか?(笑)
是非、皆さんもお試しください。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆文章を見直す際に音読をすることで、
文章の至らないところなど、
多くのことに気付くことができる。
☆気が付けば、あとは、修正をして、
改善するだけ。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
私が特許事務所を開業する前に勤めていた会社は、
アイデアを非常に大切にする会社でした。
あるアイデアが出てきたとき、
そのアイデアについて『No』と言わない
という文化があったわけです。
とはいっても、実際には、
そのアイデアは実現することが難しい・・・
普通には『No』となってしまうような
アイデアだったりすることもあるわけですが、
では、
「そのアイデアはちょっと」という、
本来は『No』というべきアイデアを、
「どうやったら『Yes』にできるのか」
を必死に考えるという文化のある会社でした。
『No』と言わずに、『Yes』とするために
必死に知恵を絞る必要に迫られるので、
仕事は本当に大変だったのですが、
非常にやりがいがあって、
とても力がつく会社でもありました。
実際に、今でも、その経験が生きているなと思います。
この仕事をしていると、ついつい、
そのアイデアは『新規性がない』、『進歩性がない』
といったように、
審査官と同じ目線で、見てしまうことがあります。
本来であれば、「どうすれば特許になるのか」を
考える立場であるはずなのに、気がつけば、
審査官のように、ふるまってしまうわけです。
つまり、『No』のアイデアに
『No』と言ってしまっているわけです。
どうしても、特許にすることができないものを
『Yes』というのはおかしいですが、
どうすれば『Yes』になるのか?
という視点をもつことが重要です。
発明の掘り起こしなどで、
ご相談をいただくことがありますが、
その際に、新規性や進歩性がないと
思えるようなアイデアであっても、
では、どういうところで工夫をすれば
特許性が出てくるのか
ということをお話するようにしています。
もちろん、ビジネスがありきの特許ですから、
特許ありき、になってしまっては困るので、
そのあたりのバランス感覚は必要だと思います。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆『No』のアイデアであっても、
『Yes』にするためにはどうするかを考える。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
平素は弊所サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、弊所では下記の日程において、夏季休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
■■夏季休業期間■■
2017年8月11日(金) から 2017年8月15日(火) まで
※ 上記期間中も、インターネットからのお申し込みは受け付けておりますが、
ご連絡に対するお返事は、緊急の場合を除き、
2017年8月16日(水)以降となる場合がございますので、
あらかじめご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
今後とも、格別のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。